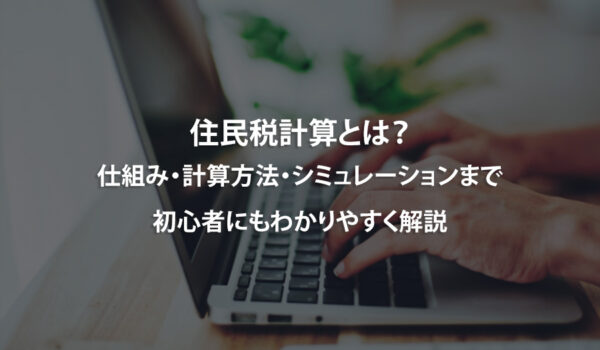
住民税計算とは、住んでいる自治体に納める「住民税」がどのように決まるのかを、所得や控除をもとに算出する考え方のことです。
給与明細や納税通知書で金額を見ても、「年収はそこまで高くないのに意外と引かれている」「昨年より増えたのはなぜ?」と戸惑う人は少なくありません。
住民税は、前年(1〜12月)の所得を基準に、所得に応じて課税される「所得割」と、一律でかかる「均等割」を合算して決まります。さらに、扶養の有無や社会保険料、生命保険料控除、医療費控除などの各種控除が反映されるため、同じ年収でも税額に差が出るのが特徴です。
また、就職・転職・退職、引っ越し、副業の開始などライフイベントによって納付方法や負担感が変わり、特に社会人2年目の6月から住民税の天引きが始まって驚くケースもよくあります。
本記事では「住民税計算とは何か」を起点に、仕組みと税率、計算の流れ、年収別シミュレーション、納付方法、非課税となる条件、よくある注意点までを、公的機関の情報を踏まえながら体系的にわかりやすく解説します。
読み終えた頃には、自分の住民税がどのように決まるのかを説明でき、家計管理や税額の見通しにも役立てられるはずです。
住民税計算とは?まず押さえる基本の考え方
住民税とはどんな税金?
住民税とは、私たちが住んでいる地域の行政サービスを支えるために納める地方税です。道路や公園の整備、教育、福祉、消防・防災といった、日常生活に欠かせない公共サービスの財源として使われています。そのため住民税は「地域社会の会費的な性質を持つ税金」とも表現されます。
住民税はひとつの税金ではなく、都道府県民税と市区町村民税の2つを合算したものです。納税者はこれらをまとめて「住民税」として自治体に納める仕組みになっています。
「所得税」との違いを理解しよう
住民税とよく混同されるのが所得税ですが、両者にはいくつか重要な違いがあります。まず、所得税は国に納める国税であるのに対し、住民税は自治体に納める地方税です。納付先が異なるため、税金の使われ方や制度設計にも違いがあります。
また、課税のタイミングにも差があります。所得税はその年の所得に対して課税されますが、住民税は前年1月から12月までの所得をもとに、翌年度に課税される仕組みです。このため、就職や転職をした翌年に住民税の負担が増え、「急に税金が高くなった」と感じるケースが多く見られます。
さらに税率構造も異なります。所得税は所得額に応じて税率が上がる累進課税ですが、住民税の所得割は原則として一律10%です。このような違いを理解しておくと、給与明細や納税通知書の内容がより分かりやすくなります。
住民税は「所得割」と「均等割」で計算される
住民税の計算は複雑に感じられがちですが、基本はとてもシンプルです。住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、所得の金額に関係なく一律で課税される「均等割」の2つを合計して算出されます。それぞれの仕組みを理解することで、住民税計算の全体像が見えてきます。
所得割とは(税率10%の仕組み)
所得割とは、前年の所得をもとに計算される住民税の中心的な部分です。課税所得金額に対して税率を掛けて算出され、標準税率は全国共通で10%と定められています。
この10%の内訳は、原則として都道府県民税4%と市区町村民税6%です。ただし、政令指定都市では内訳が異なり、都道府県民税2%・市民税8%となっています。合計の税率は同じ10%ですが、配分が異なる点が特徴です。
所得割はその名のとおり、所得が増えるほど税額も増える仕組みになっています。社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を差し引いた後の課税所得に対して計算されるため、同じ年収であっても控除の有無によって住民税額に差が生じます。
均等割とは(一律5,000円の内訳)
均等割とは、所得の金額に関係なく、一定額が一律で課税される住民税です。現在の標準額は5,000円で、内訳は都道府県民税1,000円、市区町村民税3,000円、そして森林環境税1,000円となっています。
森林環境税は、森林整備や防災対策などを目的とした国税で、2024年度から住民税とあわせて徴収されています。そのため、均等割は以前より1,000円増えた金額になっています。
均等割が所得に関係なく課税される理由は、住民税が「地域社会の費用を広く分担する」という考え方に基づいているためです。一定以上の所得がある人は、行政サービスを支える最低限の負担として均等割を納める仕組みになっています。
住民税計算の全体フロー【4ステップで解説】
住民税計算は一見すると複雑に見えますが、実際は4つのステップで整理できます。この流れを理解しておけば、納税通知書の金額やシミュレーション結果もスムーズに読み解けるようになります。ここでは、給与所得者・個人事業主の違いにも触れながら、住民税計算の基本的な流れを解説します。
ステップ① 総所得金額を求める
最初のステップは、総所得金額を把握することです。総所得金額とは、前年1月から12月までの収入から必要経費を差し引いた後の金額を指します。
給与所得者(会社員・公務員)の場合、実際にかかった経費を細かく計算するのではなく、「給与所得控除」という制度が用意されています。これは、収入に応じてあらかじめ定められた控除額を差し引く仕組みで、収入金額が大きいほど控除額も大きくなります。
一方、個人事業主やフリーランスの場合は、売上金額から実際にかかった必要経費を差し引いた金額が所得となります。このように、働き方によって総所得金額の算出方法が異なる点が重要です。
ステップ② 課税所得金額を求める
次に行うのが、課税所得金額の計算です。課税所得金額とは、総所得金額から各種所得控除を差し引いた後の金額を指します。
所得控除には、基礎控除、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、医療費控除などがあります。これらは、個人の生活状況や負担を考慮して税負担を調整するための仕組みです。
控除額が大きいほど課税所得金額は小さくなり、その結果、住民税の所得割額も低く抑えられることになります。そのため、どの控除が適用されるのかを正しく把握しておくことが重要です。
ステップ③ 所得割額を計算する
課税所得金額が算出できたら、次は所得割額を計算します。所得割は、以下の計算式で求められます。
所得割額 = 課税所得金額 × 10% - 税額控除額
ここで注意したいのが、所得控除と税額控除の違いです。所得控除は課税所得を減らす仕組みですが、税額控除は計算された税額そのものから直接差し引かれます。住宅ローン控除や寄附金控除(ふるさと納税など)が代表例です。
ステップ④ 均等割を加算する
最後に、算出した所得割額に均等割を加算します。均等割は所得に関係なく一律で課税され、現在の標準額は5,000円です。
この均等割を加えた金額が、最終的な住民税額(年額)となります。会社員の場合はこの年額を12回に分けて給与から天引きされ、個人事業主などは原則として年4回に分けて納付します。
この4ステップを理解しておけば、住民税計算の全体像を把握でき、自分の税額がどのように決まっているのかを論理的に説明できるようになります。
住民税計算で重要な「所得控除・税額控除」
住民税計算を正しく理解するうえで欠かせないのが、所得控除と税額控除の仕組みです。どちらも税負担を軽減する制度ですが、控除されるタイミングや効果の出方が異なります。この違いを理解することで、自分の住民税がなぜその金額になっているのか、またどのように負担を抑えられるのかが見えてきます。
所得控除とは?主な控除一覧
所得控除とは、総所得金額から差し引かれる控除のことで、課税所得金額を小さくする役割があります。課税所得が減るほど、住民税の所得割額も低くなります。
主な所得控除には、以下のようなものがあります(※代表的なものであり、これら以外の控除も存在します)。
- 基礎控除:一定額がすべての納税者に適用される基本的な控除
- 社会保険料控除:健康保険料や厚生年金保険料など、支払った社会保険料の全額が対象
- 扶養控除・配偶者控除:扶養している親族や配偶者がいる場合に適用される控除
- 生命保険料控除:生命保険や個人年金保険などの保険料に応じて適用される控除
- 医療費控除:年間の医療費が一定額を超えた場合に適用される控除
これらの控除は、年末調整や確定申告で申告することで適用されます。控除漏れがあると、本来よりも住民税が高くなってしまうため注意が必要です。
税額控除とは?所得控除との違い(詳細)
税額控除とは、所得割の計算後に算出された税額そのものから直接差し引かれる控除です。所得控除よりも、1円あたりの減税効果が大きいのが特徴です。
代表的な税額控除には、以下のようなものがあります。
- 住宅ローン控除:住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、一定額を税額から控除
- 寄附金控除(ふるさと納税):自治体などへの寄附額に応じて税額が軽減される制度
また、住民税特有の仕組みとして調整控除があります。これは、所得税と住民税で基礎控除や扶養控除の額に差があることによって、税負担が急に増えないようにするための調整措置です。ただし、合計所得金額が一定額を超える場合は適用されない点に注意が必要です。
所得控除と税額控除の違いを理解し、適切に申告することで、住民税の負担を無理なく抑えることができます。
住民税計算シミュレーション【年収別】
ここからは、実際の数値を使って住民税計算をシミュレーションしてみましょう。住民税は原則として自治体が計算しますが、目安を把握しておくと、給与明細の住民税額が妥当かどうかの確認や、家計管理に役立ちます。なお、実際の税額は自治体や控除の適用状況(調整控除・税額控除など)によって変動するため、ここでは概算の考え方としてご覧ください。
年収350万円・独身の場合
まずは、年収350万円の会社員(扶養なし)を想定します。条件を以下のように置きます。
- 年収:350万円
- 社会保険料:50万円(概算)
- 税額控除:なし
- 扶養:なし
- 基礎控除:43万円(住民税の基礎控除の上限額を想定)
【1】所得額(給与所得)を求める
給与所得者は、年収から「給与所得控除」を差し引いて所得額を求めます。
例として、給与所得控除を113万円(概算)とすると、
所得額 = 350万円 − 113万円 = 237万円
【2】課税所得金額を求める
所得額から、社会保険料控除と基礎控除を差し引きます。
課税所得金額 = 237万円 − 50万円 − 43万円 = 144万円
【3】所得割額を求める
住民税の所得割は、原則として課税所得金額に税率10%を掛けて算出します。
所得割額 = 144万円 × 10% = 14万4,000円
【4】均等割を加算する
均等割(標準額)を5,000円とすると、
住民税額(年額)= 14万4,000円 + 5,000円 = 14万9,000円
この年額を、会社員の場合は原則として6月〜翌5月の12回に分けて給与から天引きされます。
年収500万円・会社員の場合
次に、年収500万円の会社員(扶養なし)を想定します。条件は以下のとおりです。
- 年収:500万円
- 給与所得控除:144万円(概算)
- 社会保険料:75万円(概算)
- 基礎控除:43万円
- 税額控除:なし
- 扶養:なし
【1】所得額(給与所得)を求める
所得額 = 500万円 − 144万円 = 356万円
【2】課税所得金額を求める
課税所得金額 = 356万円 − 75万円 − 43万円 = 238万円
【3】所得割額を求める
所得割額 = 238万円 × 10% = 23万8,000円
【4】均等割を加算する
住民税額(年額)= 23万8,000円 + 5,000円 = 24万3,000円
年収が上がるほど所得額・課税所得が増え、結果として所得割が大きくなるため、住民税額も増えるイメージです。
扶養あり・控除ありの場合の違い
同じ年収でも、扶養の有無や控除の適用状況によって住民税は変わります。たとえば、配偶者や子どもを扶養している場合は扶養控除・配偶者控除が適用され、課税所得金額が小さくなるため、所得割が下がる傾向にあります。
また、生命保険料控除や医療費控除、iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)なども、課税所得を圧縮する要素です。さらに、住宅ローン控除やふるさと納税(寄附金控除)のような税額控除がある場合は、計算後の税額から直接差し引かれるため、負担がより軽くなるケースがあります。
つまり住民税は「年収だけ」で決まるものではなく、家族構成(扶養)と控除の適用状況が大きく影響します。納税通知書や給与明細を確認する際は、前年の控除申告に漏れがなかったかもあわせてチェックすると安心です。
住民税はいつ・どうやって払う?納付方法の違い
住民税は、前年(1月〜12月)の所得をもとに税額が決まり、原則として翌年6月から翌5月にかけて納付します。支払い方法は大きく分けて、会社が給与から天引きして納める特別徴収と、納税者本人が納付書などで支払う普通徴収の2種類です。働き方や収入形態によって適用される方法が異なるため、まずはそれぞれの仕組みを押さえておきましょう。
特別徴収(会社員)の仕組み
会社員や公務員などの給与所得者は、原則として特別徴収で住民税を納めます。特別徴収とは、勤務先が従業員の住民税を毎月の給与から天引きし、従業員に代わって自治体へ納付する制度です。納税者本人が納付の手続きをする必要がなく、払い忘れが起こりにくい点が特徴です。
6月開始の理由
住民税は前年の所得をもとに自治体が税額を決定し、5〜6月頃に「住民税決定通知書(特別徴収税額決定通知書)」が勤務先へ届きます。その通知内容に基づき、会社は6月分の給与から天引きを開始し、翌年5月分までの12回で納付します。つまり、住民税が6月から始まるのは、自治体の税額決定と通知のタイミングに合わせた仕組みです。
毎月の給与天引きの流れ
特別徴収では、住民税(年額)を基本的に12で割った金額が毎月天引きされます(端数調整が入る場合は、初月の6月分などで調整されることがあります)。転職・退職をすると、残りの住民税を「普通徴収に切り替えて納付」または「退職時に一括徴収」など、状況によって扱いが変わるため、退職時は会社や自治体からの案内を必ず確認しましょう。
普通徴収(個人事業主・副業)の仕組み
個人事業主やフリーランス、または副業収入があり特別徴収の対象外となる場合などは、原則として普通徴収で住民税を納めます。普通徴収とは、自治体から送付される納付書(または通知)に基づき、納税者本人が住民税を支払う方法です。
年4回納付
普通徴収では、住民税(年額)を通常年4回に分けて納付します。納付書は多くの自治体で6月頃に送られ、一般的な納期限は6月・8月・10月・翌年1月です(自治体によって多少異なります)。一括納付できる自治体もあるため、まとまった支払いが可能な場合は選択肢として検討してもよいでしょう。
電子決済・口座振替の注意点
近年は、納付書による現金納付だけでなく、クレジットカード決済、スマホ決済、地方税ポータルサイトを通じた電子納付など、支払い方法が多様化しています。ただし、電子決済は手数料が発生する場合がある点や、支払い方法によっては即時反映されないこともあるため注意が必要です。
また、口座振替は払い忘れ防止に有効ですが、登録までに時間がかかることがあります。納期限直前に申し込んでも当期分に間に合わないケースがあるため、利用する場合は早めに手続きを済ませておくと安心です。
住民税が非課税になるケースと年収目安
住民税は、すべての人が必ず納めなければならないわけではありません。一定の条件を満たす場合には、住民税が非課税となる仕組みが設けられています。非課税の判定は、前年の所得や世帯構成をもとに行われ、「所得割・均等割ともに非課税」となるケースと、「所得割のみ非課税」となるケースの2種類があります。
所得割・均等割とも非課税になる条件
所得割と均等割の両方が非課税になる場合、住民税は一切かかりません。主に、生活に必要な最低限の所得を下回る場合や、特定の事情がある人が対象となります。
一般的に、次のいずれかに該当する場合は、所得割・均等割ともに非課税となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている場合
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が一定額以下の場合
- 前年の合計所得金額が、自治体の条例で定める基準額以下の場合
非課税となる年収の目安は、世帯構成によって異なります。たとえば、同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合は、扶養人数が増えるほど非課税となる所得の上限も高くなります。
目安としては、単身世帯よりも、夫婦世帯、夫婦+子ども世帯のほうが、非課税となる年収ラインは高くなります。ただし、これらの金額は自治体ごとに条例で定められているため、実際の判定基準はお住まいの市区町村によって異なる点に注意が必要です。
所得割のみ非課税となるケース
一定の所得以下の場合、所得割のみが非課税となり、均等割だけを納めるケースがあります。これは、課税所得が基準額を下回っているものの、均等割の非課税要件までは満たしていない場合に該当します。
この場合の住民税は、「均等割だけ払う」状態となり、税額は原則として5,000円(都道府県民税・市区町村民税・森林環境税の合計)です。
所得割が非課税となる年収の目安も、世帯構成や自治体によって異なりますが、単身世帯であればおおむね100万円前後が一つの基準とされることが多くなっています。扶養親族がいる場合は、その分だけ基準額が引き上げられます。
住民税の非課税判定は、年末調整や確定申告の内容をもとに自治体が行います。自分が非課税に該当するかどうか不安な場合は、納税通知書の内容を確認するか、自治体の窓口で確認すると安心です。
住民税計算でよくある疑問・注意点
住民税計算について調べていると、「自分で計算しなければならないの?」「通知された金額が合わないのはなぜ?」など、さまざまな疑問が出てきます。ここでは、検索ユーザーが特に不安に感じやすいポイントをQ&A形式で整理し、住民税計算に関する注意点をわかりやすく解説します。
住民税は自分で計算する必要がある?
結論から言うと、住民税は原則として自分で計算する必要はありません。住民税は「賦課課税方式」が採られており、年末調整や確定申告の内容をもとに、自治体が税額を計算し、納税者に通知します。
ただし、自分で計算方法を理解しておくと、納税通知書の金額が妥当かどうかを確認できるほか、年収や控除が変わった場合の住民税額を事前に予測することができます。特に転職・退職・副業開始などのタイミングでは、目安を把握しておくと安心です。
引っ越しした場合、どこに納める?
住民税は、その年の1月1日時点で住民票がある自治体に納める仕組みです。年の途中で引っ越しをした場合でも、その年の住民税は1月1日に住んでいた市区町村に納付します。
たとえば、4月に別の自治体へ引っ越した場合でも、その年の住民税は旧住所地の自治体から課税されます。新しい住所地で住民税を納めるのは、翌年度分からになります。この点を知らないと、「引っ越したのに前の自治体から請求が来た」と混乱しやすいため注意が必要です。
計算結果と通知額が違うときの考え方
シミュレーションで計算した金額と、自治体から届いた住民税決定通知書の金額が一致しないことは珍しくありません。その主な理由として、以下のような点が挙げられます。
- 調整控除や税額控除(住宅ローン控除・寄附金控除など)が反映されている
- 端数処理や月割計算による差
- 社会保険料や控除額を概算で計算している
- 自治体独自の条例や軽減措置が適用されている
大きな差がある場合や内容に不明点がある場合は、納税通知書に記載されている課税内容を確認し、必要に応じて自治体の税務担当窓口に問い合わせるとよいでしょう。
払い忘れた場合の延滞金リスク
住民税を納期限までに納付しなかった場合、延滞金が発生する可能性があります。延滞金は、滞納した税額と滞納日数に応じて計算され、納付が遅れるほど負担が大きくなります。
特に普通徴収の場合は、自分で納付する必要があるため、払い忘れに注意が必要です。延滞が続くと、督促状の送付や財産差押えなどの手続きが取られることもあります。
こうしたリスクを避けるためには、口座振替の利用や、スマホ決済・電子納付の活用など、払い忘れを防ぐ仕組みを取り入れることが有効です。納期限を把握し、計画的に納付するよう心がけましょう。
まとめ
住民税計算とは、前年(1月〜12月)の所得をもとに、所得割と均等割を合算して住民税額を算出する仕組みのことです。所得割は課税所得に一律10%を掛けて計算され、均等割は所得に関係なく一定額が課されます。そのため、住民税は年収だけで決まるものではなく、社会保険料や扶養の有無、各種所得控除・税額控除によって大きく変わります。また、会社員は特別徴収、個人事業主などは普通徴収と、働き方によって納付方法や支払いタイミングも異なります。非課税となるケースや、所得割のみが非課税になるケースを知っておくことも重要です。住民税は原則として自治体が計算しますが、仕組みを理解しておくことで、納税通知書の内容確認や将来の税負担の見通し、家計管理に役立てることができます。住民税額に不安がある場合は、早めに内容を確認し、必要に応じて専門サービスや相談窓口を活用すると安心です。
 お問い合わせ
資料ダウンロード
お問い合わせ
資料ダウンロード



